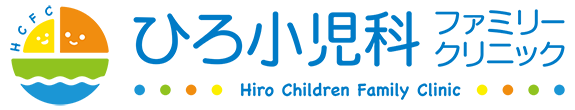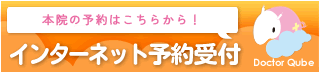※トップページへ戻るには、『本院』をクリックしてください。
予防接種対応時間帯につきまして(令和7年11月21日発信)
●New(11月21日)1歳以上のワクチン接種(ロタワクチン、BCGを除く)について、土曜日を除く一般診療時間帯(全時間帯)で対応させていただきます。
なお、1歳未満のお子様の接種、ロタワクチン接種、BCG接種をご希望の方は、これまで通りに予約ワクチン枠での接種にご協力をお願い致します。→水曜日、木曜日、金曜日の午後2時〜3時15分。
インフルエンザワクチン接種(令和7年11月21日発信)
●New(11月21日)インフルエンザ予防接種(注射タイプ)の予約を再開させていただきます。
Webでのご予約をお願い致します。
なお、在庫がなくなり次第、予約対応を終了させていただきますのでご理解のほどお願い致します。
●経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの予約受付は終了しました。
おたふくかぜワクチン接種(令和7年11月7日発信)
メーカーからの供給が見込まれないため、「おたふくかぜワクチン」の予約を一時中止しております。
ご迷惑をおかけします。
予防接種の考え方

病気はかかってしまったら速やかに治療する事が非常に重要です。またそれと同時に、病気にかからないように努めることもとても大切なことだと思います。日常の手洗い、うがいやマスク着用はご家庭で実施可能な予防手段です。
医療機関での有効手段として予防接種が存在します。特に重症な病気の場合は、かかってしまってからでは治療が困難ばかりでなく、時に生命にかかわることもあります。病気にかからないようにするために予防接種は非常に重要な手段と考えます。

2013年度から肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの定期接種が導入され、それ以降これらの菌による細菌性髄膜炎はほとんどみられなくなりました。

予防接種には注射による恩恵(メリット)と注射による副反応(デメリット)があり、それらを接種する医師と接種を受ける患者様およびそのご家族が理解する必要があります。
ネルソン小児科学第19版には、予防接種は最も有益かつ費用対効果の高い疾患予防法の1つである。小児期にみられるワクチンで予防可能な他の疾患(VPD)の大半は当該ワクチン開発と比較した場合に年間発生率が99%以上減少している、と記されています。このように予防接種は、子どもたちの命を守る非常に有効な手段であることを忘れてはなりません。
子どもたちへの予防接種による健康増進にこれからも努めていきたいと思います。
院長 神山 浩
予防接種について
生ワクチンと不活化ワクチン
例えばロタウイルス生ワクチンでは、ロタウイルス胃腸炎の症状である白い便などが出現する可能性があります。
一方、不活化ワクチンでは基本的にワクチン対象疾病の症状が出現する可能性はありません。
New 四種混合、ヒブ感染症の各ワクチンの取り扱いついて(令和7年9月19日発信)
- 第1期3回接種まで四種混合ワクチン、ヒブ感染症ワクチン接種を終えているお子様:第1期追加接種は、五種混合ワクチン接種の対象となります。
- 第1期3回接種まで四種混合ワクチンを、かつ、第1期追加接種までヒブ感染症ワクチン接種を終えているお子様:四種混合の第1期追加接種は、五種混合ワクチン接種の対象となります。
1歳までの接種が推奨されている予防接種(令和7年7月1日発信)
キーワードは生後2か月
1か月健診を受けられた後の下記ワクチンのご予約(「2か月齢」)を推奨いたします。
- 肺炎球菌ワクチン(20価ワクチン)
- B型肝炎ワクチン
- 五種混合ワクチン
- ロタウイルスワクチン
初めての接種後のワクチン接種スケジュールについてアドバイスをさせていただきますので、お任せください(ご自身で接種スケジュールを立てる必要はございません)。
生後2か月の初めてのワクチン接種のご予約もWEB予約をお願い致します。

五種混合(DPT-IPV-Hib)
ワクチンの種類:不活化
第1期初回標準接種月齢:生後2か月〜7か月未満の間。20日〜56日の間隔をおいて3回。
第1期追加標準接種月齢:初回接種終了 → 6〜18か月の間隔をおいて1回。
受けることが可能な年齢:生後2か月〜7歳6か月未満
小児の肺炎球菌感染症
ワクチンの種類:不活化
初回標準接種月齢:生後2か月〜7か月未満の間。27日以上の間隔をおいて3回。
追加標準接種月齢:初回接種終了 → 60日以上の間隔をおいて生後12か月〜15か月に1回。
受けることが可能な年齢:生後2か月〜5歳未満
B型肝炎
ワクチンの種類:不活化
1、2回目標準接種月齢:生後2か月 → 27日以上の間隔をおいて2回。
3回目標準接種月齢:2回接種終了 → 生後7〜8か月(1回目から139日以上の間買うをおいて)に1回。
受けることが可能な年齢:1歳未満
ロタウイルス感染症
ワクチンの種類:生(経口)
特異的副反応:腸重積症(ただし発症は非常に稀です)
◉1価ワクチン
接種回数:2回
生後2か月〜24週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて2回
*初回接種は出生14週6日まで
受けることが可能な年齢:出生6週0日〜24週0日後
◉5価ワクチン
接種回数:3回
生後2か月から〜32週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて3回
*初回接種は出生14週6日まで
受けることが可能な年齢:出生6週0日〜32週0日後
BCG
ワクチンの種類:生
標準接種月齢:生後5か月〜8か月未満の間に1回。
受けることが可能な年齢:1歳未満。
Hib(ヒブ)感染症(令和7年9月19日発信)
四種混合(DPT-IPV)(令和7年9月19日発信)
1歳以上での接種が推奨されている予防接種
キーワードは早期接種
麻しん(はしか)流行は予防接種の徹底でほとんど認めませんが、成人で時々小流行を認めることがあります。乳幼児期の麻しん感染では重症肺炎の合併などが懸念され、1歳になりましたら速やかな麻しん接種を推奨します。
日本脳炎の標準接種年齢は3歳以降となっておりますが、生後6か月から接種可能になっています。

麻しん・風しん混合(MR)
ワクチンの種類:生
第1期標準接種年齢:1〜2歳未満の間に1回。
第2期標準接種年齢:年長組在籍中に1回(小学校入学年度の前年度4月〜3月の間に1回)。
水痘
ワクチンの種類:生
1回目標準接種年齢:1歳〜1歳3か月未満の間に1回。
2回目標準接種年齢:1回目接種から6〜12か月の間隔をおいて1回。
受けることが可能な年齢:1歳〜3歳未満
日本脳炎
ワクチンの種類:不活化
第1期初回標準接種月齢:3歳の間に6日〜28日の間隔をおいて2回。
第1期追加標準接種月齢:4歳の間で、初回接種終了後おおむね1年後に1回。
第1期の受けることが可能な年齢:生後6か月〜7歳6か月未満
第2期標準接種月齢:9歳の間に1回。
第2期の受けることが可能な年齢:9歳〜13歳未満
*日本脳炎ワクチンは生後6ヶ月からの接種が可能です。当クリニックでは生後6ヶ月からの接種に対応しています。
二種混合
ワクチンの種類:不活化
第2期標準接種年齢:11歳の間に1回。
受けることが可能な年齢:11歳〜13歳未満
*女児では小学校6年生になりましたら子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防)接種が可能になります。
子宮頸がんワクチンは当クリニックで接種可能ですのでご相談ください。
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
ワクチンの種類:不活化
受けることが可能な年齢:小学校6年生から高校1年生相当の女子
*小学校6年生になりましたら子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防)接種が可能になります。
子宮頸がんワクチンは当クリニックで接種可能ですのでご相談ください。
予防接種スケジュール
また、その後の予防接種スケジュールについても、「何をいつ受ければ良いか」について、「日付入りの具体的なスケジュール表」をお渡ししますので、ご心配なくご来院いただきたいと思います。
麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種の考え方(令和6年3月18日発信)
国立感染症研究所感染症疫学センター(2018年4月17日発信)によれば、
以下の「注意点」と「可能な限り早めのMRワクチン接種が推奨される者」として記されています。
注意点
- 麻疹含有ワクチンの接種歴は記録で確認すること(記憶はあてにならない。接種の記録がなければ、受けていないと考える)。
- 1歳以上で2回の麻疹含有ワクチン接種記録がある者は受ける必要はない。
可能な限り早めのMRワクチン接種が推奨される者
- 近隣で麻疹患者の発生が認められる、生後6〜11か月児(緊急避難的な場合に限る)。
- 0歳児の家族
- 2歳以上第2期定期接種対象期間に至る前の幼児で、麻疹含有ワクチン未接種あるいは接種歴不明者
- 小、中、高、大、専門学校生等で、麻疹含有ワクチン未接種あるいは1回接種あるいは接種歴不明者
以上をふまえた当クリニックの見解(令和6年3月18日)
- 母子手帳に1歳でのMRワクチンの接種歴があれば、小学校就学前の幼児に対する早めのワクチン接種は必ずしも必要ない(不要ということではない)。
- 6か月未満の乳幼児に対しての接種は推奨されておらず、接種歴不明の同居家族がいればその対象者(父親、母親等)の接種が推奨される。
- 母子手帳に2回のMRワクチンの接種歴があれば、小、中学生に対する早めのワクチン接種は必ずしも必要ない(不要ということではない)。
当クリニックの対応について(令和6年3月19日更新)
- 0〜1歳児のご両親に対するMRワクチン接種については、検討すべきと考えます。令和6年3月19日現在、ご両親の接種可否に関する電話でのご相談はお受けしておりません。また、小児に対する定期MRワクチンが確実に行われることを目的として、成人に対する自費でのMRワクチン接種は受付しておりません。
- 2歳児以上のご両親もしくは高校生以上の抗体検査あるいはMRワクチン接種の可否についてのご相談は、上記の見解を含めお受けすることができません。